 専門部会・委員会・連絡会活動計画
専門部会・委員会・連絡会活動計画
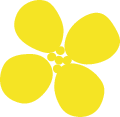 令和7年度 活動計画
令和7年度 活動計画
地域の方々との日頃の温かい交流が活動の基本であることを再度確認し、研修や交換民児協で得られた情報や知識を自身の地域の活動に還元することを目指します。
- ①研修では、「ひきこもり」と「自殺の予防」について民生委員・児童委員との関わり方を勉強します。
- ②交換民児協は昨年度に引き続き、市外の民児協との交流を可能とし、より様々な取組を学べるようにします。
- ③各部会、連絡会、委員会と情報を共有し、必要に応じ関係機関とも連携して課題に取り組みます。
3年間を1つの期間としてとらえ、最終年の本年も高齢者福祉問題に取り組みます。
- ①高齢者福祉に関する現状や課題について知識を深めるため、研修会を開催します。
- ②各委員の高齢者見守り等の活動・経験談を共有し、今後の活動に活かしていきます。
「障害のある人が地域で共にいきいき活動できる社会を築く」という理念のもと、取り巻く課題を明確にできるよう活動を行います。今年度は次の4点を行います。
- ①障害児者の課題と取組内容に関する研修会を開催します。
- ②「草津市いきいきふれあい大運動会」などの行事に参加・協力し、各支援団体と交流を深めます。
- ③障害児者施設を訪問し、実情を学びます。
- ④「ふくふくサロン」に継続して参加・協力し、各支援団体と交流を図り課題を検討します。
- ①3年目の括りとして、児童委員としての日々の活動に生かせる研修などを実施します。
- ②主任児童委員連絡会との意見交換会を通して双方の連携を深めます。
- ③児童福祉関連施設での現地研修を実施します。
部会活動3年目の令和7年度は、人権・同和(同法融和)対策運動と位置づけ、取組の更なる推進を展開していきます。日本国憲法は、基本的人権を保障し、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と謳っています。部会での意見交換、研修会等で感じ学んだ教訓を活かしながら、未だ存在する差別の実態に真摯に受け止めながら、「人権とは」「同和(部落解放)とは」を、委員として日々問いかけ、人としてその大切さに磨きをかけることを重点に取組の強化を図ることとします。
- ①部会では、学区における人権学習をはじめとして、研修会の成果や教訓から、学区全体の地域力となる人材の育成、運動の活性化に努めます。
- ②研修会では、市の人権政策推進の立場を堅持し、滋賀県人権センターとの連携も考えます。また、「差別のない社会」を意識し、フィールドワークに取り組みます。
「民生委員・児童委員ってどんな活動をしているの?」という市民からの声に、ホームページの活用を進めるとともに、民児協活動紹介パネルの作成と草津市役所1階ロビーでの展示をしながら、民生委員・児童委員活動の周知を図ります。
また、草津市民児協広報紙「こばと」の発行、ホームページによる情報発信等、有効的な広報活動を行います。
- ①草津市民児協活動事例集「光もとめて」第37集の編集と発行、学区定例会での事例研修教材としての有効活用を進めます。
- ②民生委員・児童委員活動の活動内容を草津市民児協広報紙「こばと」に掲載して発行、全戸に配布をします。
- ③ 14学区の民児協活動紹介パネルを作成し、民生委員・児童委員活動の周知を図るとともに、市民向けアンケート調査を行い啓発活動に努めます。
- ④広報委員の更なる資質向上を図るため、研修会を行います。
- ⑤草津市および草津市社協のホームページに掲載している民生委員・児童委員に関する内容の充実を図り、閲覧者の増加につながるよう努めます。
令和7年度は改選の年にあたり、この3年間の活動の締めくくりとなるような研修を企画し、開催します。
- ①総会研修として、手話シンガーソングライターyokkoさんによるライブ型人権研修を行います。
- ②全体研修後を開催し、講演後委員間の懇談・交流の場を設けます。
市域や学区の活動を通じて、地域担当の民生委員・児童委員と協力・連携し、子どもの福祉活動の充実を図ります。
- ①定例連絡会の充実
- ②懇談会など市内小・中学校との連携
- ③研修会の開催
- ④関係機関等主催の研修会に積極的に出席、研修会後は内容を振り返り、課題の共有を図る
- ⑤主任児童委員の啓発活動の推進(10か月健診の見守りなど)
- ⑥湖南地域4市主任児童委員交流会の開催
- ⑦関係機関との連携強化
- ⑧児童福祉部会との意見交換会
- ⑨教育委員会との意見交換会





